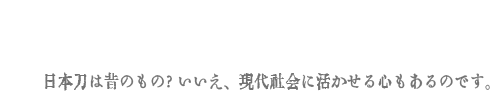日本刀を入手する際に気になるポイントの一つが、本当に価値のある刀なのかどうかという点です。鑑定書は、その刀がどの時代の誰によって作られたかを証明するものであり、「真贋判定」の根拠にもなります。初心者にとっては専門用語が多く、敷居が高いと感じられるかもしれませんが、基本的な「確認方法」と「注意点」を押さえておけば、日本刀の世界をより安心して楽しめるはずです。
鑑定書にはいくつかの種類が存在します。代表的なものとしては、公益財団法人日本美術刀剣保存協会(NBTHK)が発行するものや、刀剣博物館など公的機関や権威ある団体が認定しているものです。これらの機関が発行する鑑定書は、日本刀の作者や作刀年代、刀身の流派や特徴などを詳細に記載しており、比較的信頼度が高いと言えます。ただし、個人や規模の小さい刀剣商が独自に作成した書面の場合、公的な鑑定書とは別物であるケースもあるので注意が必要です。初心者が購入する際は、なるべく公的な鑑定書が付属している刀を選ぶのが無難でしょう。
鑑定書の「確認方法」としては、まず記載されている作者名や作刀年代が実際の刀身と矛盾していないかを見ます。例えば刀身の銘(めい)が「備前長船」とあるのに、鑑定書には「肥前国忠吉」と書かれていたら、不一致が生じていることになります。また、刀身の長さや反り具合、刃文(はもん)の形状など、外観的特徴も鑑定書と照らし合わせて確認しましょう。もし初心者だけで判断が難しい場合は、信頼できる刀剣店や専門家に見てもらうのが安心です。複数の専門家の意見を取り入れることで、より正確に真贋を見極めることができます。
一方で、「真贋判定」は鑑定書があるからといって万全というわけではありません。古い時代の鑑定書や個人作成の証明書の場合、後になって再鑑定をしたら結果が変わってしまったという例もあるからです。日本刀の世界では、時代によって流派や作風が変化しており、それらを見極めるためには膨大な知識と経験が必要です。近年では研磨技術の発達や贋作の巧妙化によって、見分けが一層難しくなっている面もあります。そのため、いくら鑑定書が付いていても、鵜呑みにせず、実際の刀身を丁寧に観察し、必要に応じて再鑑定を検討することが大切になります。
また、初心者が日本刀を買うときに気を付けたい「注意点」としては、価格や保存状態の確認も挙げられます。真贋判定以前に、刀身にサビや欠けがあったり、外装(拵え)が破損していたりする場合は、想定以上の修理費用がかかるかもしれません。鑑定書に記載されていない細かなダメージや、名のある刀匠の作とされていながら実際の出来が伴わないケースもあるため、現物をしっかりと確認することが重要です。さらに、修復や研磨を依頼する際には、依頼先の技量や信頼度を見極めなければ、本来の刀剣としての美しさを損なってしまうリスクも伴います。
もう一つの注意点は購入ルートです。個人売買やインターネットオークションなどを利用する場合は、鑑定書の真偽を確かめる手段が限られることが多く、トラブルに巻き込まれる可能性が高まります。なるべく実店舗を構えた刀剣商や、歴史ある美術商を利用し、アフターサービスの有無なども含めてチェックしましょう。信用のおける専門店であれば、鑑定書の有無だけでなく、刀剣を理解するための基礎知識を教えてくれることもあります。
本コラムでは、日本刀の真贋判定と登録証について解説しました。日本刀を購入する際は、鑑定書の記載内容と刀身の特徴を照合しつつ、真贋判定が万全でないことも認識しておきましょう。個人や小規模な店が独自に発行する書類の場合、公的鑑定とは別物であるケースがあるため注意が必要です。購入前には複数の専門家の意見を取り入れ、修理費や信頼できる販売店の選定なども含めた総合的な情報収集を行うことが大切です。